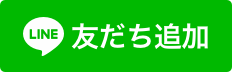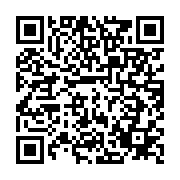公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2025年8月6日
サラ金や昔の借金、消費者金融やカードローン、銀行の時効は5年?それとも10年?
借金にも時効がある
借りたお金は返さなくてはいけないのが大原則ですが、借りたお金を返さなくてもよくなる例外があり、それが借金の消滅時効といわれるものです。
原則的にサラ金やカード会社などの貸金業者から個人がお金を借りた場合は5年で時効になります。
よって、借金を返せなくなった場合でも5年が経過すると時効となり、借りたお金を返さなくてもよくなることがあります。
ただし、借りるときから時効目的で返すつもりがないと詐欺になる可能性があるので要注意です。
返済をしていない期間はずっと遅延損害金が増えていきますので、元金よりも遅延損害金の方が多くなっているような場合も少なくありません。
しかし、時効が成立した場合は膨れ上がった利息や遅延損害金だけでなく、残っている元金についても一切支払う必要がなくなります。
2020年(令和2年)4月1日以降に発生した債権については、改正民法の適用があります。
改正民法では「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間権利を行使しないことで時効が成立すると規定されました。
通常の債権者であれば、契約時に返済期限を決めて、その期限までに返済がなかった場合は権利を行使することができることを知っているので、契約で定めた期限から5年が経過すれば時効が成立することになります。
消滅時効期間が5年と統一されたことによって、商事債権の5年、その他の短期消滅時効の規定がなくなりました。
ここがポイント!
民法の改正によって、時効期間が5年に統一された
消滅時効の起算点
どの時点から5年経過すれば時効が成立するのかが非常に重要ですが、借金の消滅時効の起算点は期限の利益喪失日です。
期限の利益喪失日というのは「分割払いができなくなった日」のことで、契約の際に期限の利益が喪失する事項があらかじめ定められています。
一般的には「2回分滞納したら期限の利益が喪失する」といった約款が契約書の裏面などに記載されています。
ただし、時効かどうかの判断をする際は時効の起算日が正確に分からなくても、ご自分の記憶で最後に返済してから5年以上経過していれば時効の可能性があると判断することになります。
例えば、平成20年1月に借入れをして、平成23年1月で返済が滞った場合、5年後の平成28年3月に時効期間が経過したと推測できます。
ただし、最後の返済から5年が経過する前に債権者が裁判上の請求をしてきたり、債務者が借金の一部を返済した場合は債務承認となり時効が中断(更新)します。
よって、時効の中断(更新)事由がない場合は、最後に返済してから5年以上経過していれば時効の可能性があります。
ここがポイント!
消滅時効は期限の利益喪失日からスタートする
時効がもともと10年の場合
債権者が貸金業者や銀行などの株式会社であれば時効期間は5年です。
これに対して、債権者が信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構、日本学生支援機構などの場合は時効期間は10年となります。
あわせて読みたい
これは、信用金庫などは営利を目的とした組織ではないからです。
しかし、たとえ債権者が信用金庫など営利を目的とした組織でなくても、債務者が会社や個人事業主である場合は商事債権となり時効期間は5年になります。
また、貸付目的(事業資金など)によっても時効期間が5年になる場合があるので、債権者が営利を目的とした組織ではないからといって時効が10年とは限りません。
ただし、民法改正によって、2020年(令和2年)4月1日以降に発生した債権は、商事債権かどうかにかかわらず5年で時効になります。
ここがポイント!
債権者が営利を目的とした組織でないと時効期間が10年になる場合がある
時効が5年から10年に延長される場合
債権者から裁判などを起こされて判決などを取られてしまうと、時効が10年延長されてしまいます。
判決などを債務名義といい裁判上で和解をした場合なども含まれます。
主な債務名義
- 確定判決
- 和解調書
- 仮執行宣言付支払督促
- 調停調書(和解に代わる決定)
確定判決というのは債権者から訴訟を起こされ、原告の請求が認められた場合に出るもので、和解調書は裁判上で分割払いの話合いが成立した場合です。
仮執行宣言付支払督促というのは、裁判手続きの一種で書面審査だけで判決と同じ効力を手にすることができるものです。
調停調書は返済が苦しくなった債務者の方から簡易裁判所に民事調停や特定調停の申し立てをした場合です。
あわせて読みたい
債務名義を取得されている場合は時効が5年から2倍の10年に延長されます。
もし、債務名義を取られた後に返済をしている場合は最後の返済から10年となります。
債務名義を取られると債権者は債務者の預貯金や給与の差し押さえができるようになりますが、債権者から強制執行をされると時効がそこからさらに10年延長します。
よって、債務名義を取得されている場合でも債務名義の確定から10年以上経過していれば時効の可能性があるので、いつ判決などの債務名義を取られたのかがポイントになります。
判決などの債務名義には必ず事件番号が付けられているので、事件番号が分かれば何年前に取られた債務名義かがわかります。
裁判の事件番号
◯◯簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号
債権者からの請求書には債務名義の事件番号が記載されているケースもあるので、そこで年数が確認できれば時効の可能性があるかどうかわかる場合があります。
ここがポイント!
判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年に延長される
時効がリセットされてしまうこともある
借金の時効は5年ですが、例外的に時効がリセットしてしまうことがあり、これを債務承認による時効の中断(更新)といいます。
2020年(令和2年)の民法改正によって、これまでの時効の中断が「更新」と「完成猶予」に分けられました。
「更新」とはリセットの意味で、時効がゼロから再スタートなります。
これに対して「完成猶予」は時効が先延ばしにされるという意味です。
あわせて読みたい
例えば、最後の返済が2013年で時効成立が2018年のケースでも、2017年に債務承認による時効の中断(更新)があると2022年までは時効になりません。
具体的に時効が中断(更新)してしまう代表的なケースは以下のとおりです。
時効が中断(更新)する行為
- 借金の一部を支払う
- 実際に支払いをしていなくても和解書や示談書にサインする
- 和解書などの取り交わしをしていなくても、返済条件の話をする
- 具体的な返済条件の話をしていなくても、支払う意思があることを伝える
上から順に債務承認に該当する度合いが高いです。
借金の一部を実際に支払ってしまった場合は完全にアウトです。
つまり、返済したことによって時効が更新してしまいます。
和解書や合意書などの取り交わしをしたような場合も同様です。
現金の振り込みや書面の取り交わしをしていなくても、電話などで返済条件の話を具体的にしているような場合は時効が更新するケースがあります。
返済するつもりがあることだけを伝えて、具体的な話をしていないような場合は債務承認に該当するかどうか微妙なケースもあります。
債権者がいきなり自宅まで訪問してきて、半ば強制的にその場で現金を支払わされたり、返済の約束をさせられたような場合は例外的に債務承認には該当しないという裁判例もあります。
よって、ご自分で判断せずにまずは専門家にご相談ください。
ここがポイント!
債務承認に該当する行為があると、それまでの時効期間がリセットされてしまう
時効を主張するには
注意しなければいけないのは、時効によって債務者が借金を支払わなくてよくなるとはいっても、返済をしなくなってから5年経過したからといって自動的に消滅時効が成立するわけではないという点です。
なぜなら、消滅時効を成立させて借金の支払義務をなくすためには、借主である債務者が貸主である債権者に対して「借金はすでに時効なので支払いません」と意思表示しなければならないからです。
この意思表示を消滅時効の援用といいます。
よって、借金の支払いをしたくないのであれば、貸主である債権者に対して、きちんと消滅時効を書面などで通知する必要があります。
もし、ご自分でするのが不安であれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
代理人による時効援用なら
当事務所にご依頼された場合、当事務所が代理人となって時効の援用をおこなうことができます。
当事務所にご来所頂けない遠方の方は、ご来所不要の内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼件数8000人以上
こちらはLINE、メールなどで請求書の画像を送って頂ければ、当事務所にお越し頂くことなく、内容証明の発送までを代行するサービスです。
ここがポイント!
借金の消滅時効を援用するのであれば、きちんと意思表示しなければいけない
意思表示の方法
消滅時効の援用方法については特に決まりはありません。
直接、債権者の面前で時効の主張をしても構いませんし、電話で伝えても構いません。
しかし、口頭でのやり取りだと、あとで言った言わないの水掛け論になる可能性があったり、債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるのでお勧めできません。
よって、消滅時効を援用したいのであれば、書面で通知するのが安全です。
さらに、普通郵便だとあとから届いていないと言われる可能性があるので、消滅時効の援用は配達証明付の内容証明郵便でおこなうのが一番安全で確実です。
あわせて読みたい
ここがポイント!
消滅時効の援用は、配達証明付の内容証明郵便でおこなうのが安全
信用情報機関への影響
時効の援用をすることで自分の信用情報に傷が付くのか心配される方が多いです。
しかし、時効の援用をすることで新たに事故情報が掲載されることはありません。
JICC、CICなどの信用情報機関に、延滞などの事故情報が載ることを一般的に「ブラックリストに載る」等といいますが、この状態は借金を数ヶ月延滞することで発生します。
あわせて読みたい
つまり、借金を滞納している時点ですでにブラックになっているのであり、その状態で時効の援用をしても新たに事故情報が掲載されることはありません。
それどころか時効の援用をすることで信用情報が回復するので、信用情報はむしろきれいになります。
ただし、事故情報が消えるまでの期間は信用情報機関によって異なります。
事故情報が抹消されるまでの期間
- JICC ➡ 1~2か月で抹消される
- CIC ➡ 5年で抹消される
※ただし、CICも「異動年月日」が登録されていない場合はすぐに信用情報が回復することがあります
JICCでは、登録業者から時効成立の報告があれば、すぐに事故情報を抹消してくれる運用です。
これに対して、CICでは時効が成立しても5年間は事故情報が残ります。
当初の借入先がすでに貸金業を廃業していたり、債権が転々と譲渡されて現在の債権者が非貸金業者の場合は、すでに信用情報自体はきれいになっていることがあります。
これは信用情報機関に登録できるのが、現に貸金業登録を受けている会社に限定されるからです。
よって、債権譲渡があった場合、CICでは5年、JICCでは1年で譲渡会社のブラックリストが削除されます。
紛らわしいですが債権回収会社(サービサー)は、あくまでも借金の回収を専門におこなう会社であって貸金業者ではありませんので、債権回収会社の名前で事故情報が載ることはありません。
ただし、信用情報に事故情報が載っていないからといって、借金の支払い義務までなくなったわけではないので、現在の債権者から請求が来ている以上は時効の援用をおこなう必要があります。
あわせて読みたい
借金の時効と司法書士
司法書士は債務整理の一環として、借金が時効になっていれば債権者に対して、消滅時効の援用をおこないます。
あわせて読みたい
行政書士も内容証明郵便の作成をすることができますが、行政書士が債権者と借金に関する交渉をおこなうことは一切できません。
これに対して、司法書士は債務者の代理人となって内容証明郵便を出し、債権者と直接交渉することができるので、借金の消滅時効の通知は司法書士にお願いするのが安全です。
当事務所は、これまでに1万人以上の借金問題を解決しているので、お気軽にご相談ください。
ここがポイント!
内容証明郵便による消滅時効の援用は、司法書士にお願いするのが安全
消滅時効援用の料金
報酬
1社あたり5万円(+消費税+内容証明の郵便代)
※現在、相手方から裁判所に訴訟もしくは支払督促を起こされている場合は1万円を追加します
※消滅時効の主張が認められた場合でも別途、成功報酬はかかりません
当事務所に依頼した場合の流れ
- 【来所相談】
- ※電話、LINE、メールでご予約ください
- 【取引履歴の開示請求】
- ※司法書士が貸金業者から取引履歴を取り寄せます
- 【内容証明郵便の発送】
- ※司法書士が代理人となって貸金業者に内容証明郵便を送付します
- 【消滅時効成立の確認】
- ※司法書士が貸金業者に対して消滅時効の成立を争うかどうか確認します
- 【消滅時効の完成】
- ※貸金業者が消滅時効を認めれば借金の支払義務がなくなります
業者別の対応
ア行
- アイアール債権回収(アコム、DCキャッシュワン、三菱東京UFJ銀行)
- ITO総合法律事務所
- アイフル
- アウロラ債権回収(SKインベストメント、合同会社エムシーフォー、ジュピター合同会社、CFJ)
- あおぞら債権回収
- アコム
- アビリオ債権回収(アットローン、三洋信販、シティカード、ジャックス、プロミス、モビット、レイク)
- アペンタクル(ワイド)
- アルファ債権回収(新生フィナンシャル、日本学生支援機構)
- 礎総合法律事務所(旧:鈴木康之法律事務所)
- AG債権回収
- エイワ
- SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販)
- SMBC債権回収(三井住友銀行グループ)
- NHK
- NTS総合弁護士法人
- エフエムシー(アーク虎ノ門法律事務所)
- エムアールアイ債権回収(エポスカード、ゼロファースト、丸井)
- エムズホールディング
- エムテーケー債権管理回収(CFJ、ディック、三和ファイナンス、ポケットカード)
- エムユー信用保証
- エムユーフロンティア債権回収(モビット、UFJニコス)
- エーシーエス債権管理回収(イオンクレジットサービス)
- 沖縄債権回収サービス
- オリンエントコーポレーション(オリコ)
- オリンポス債権回収(MKイプシロン、クリバース、CFJ、武富士、ディック、ラックスキャピタル)
サ行
- 札幌債権回収
- JFRカード(大丸カード)
- 子浩法律事務所(MUニコスクレジット、JCBカード、ドコモ、三菱UFJニコス)
- シティックスカード
- ジャックス債権回収サービス
- ジャパントラスト債権回収
- シンキ(新生パーソナルローン)
- 新生フィナンシャル(レイク)
- シーエスジー(アエル、クリバース、センチュリー、日本プラム)
- CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマット)
- しんわ
- 駿河台法律事務所
- セゾン債権回収(クレディセゾン)
タ行
ハ行
- パルティール債権回収(アプラス、楽天カード、イオンクレジットサービス、武富士)
- 引田法律事務所
- 富士クレジット
- プライメックスキャピタル(旧キャスコ)
- ベル債権回収
- 保証協会債権回収
マ行
- メザニンファンド3号投資事業有限責任組合(武富士)
- みずなら総合法律事務
- 三菱HCキャピタル債権回収
ヤ行
- ユー・エス・エス(新洋信販)
ラ行
- ライズ綜合法律事務所
- ラックスキャピタル
- リンク債権回収
- れいわクレジット管理(三菱UFJニコス)
よくある質問
-
借金にも時効があるって本当ですか?
-
借金にも時効がある
借りたお金は返さなければいけないのが大原則ですが、それでも消滅時効の適用があります。
時効制度の趣旨は、権利の上に眠る者を保護しないとか、証拠を長期間にわたって保全することの困難さを救済するためといわれています。
よって、お金を貸したからといって永久的に支払義務が続くわけではなく、債権者である貸主が請求を一定期間せず、かつ、債務者である借主が一定期間弁済をしなかった場合は時効が成立します。
-
借金は何年で時効になりますか?
-
借金は5年で時効になる
友人や親戚など個人間の借金の時効は10年ですが、サラ金やカード会社からの借金は5年で時効になります。
ただし、過去に債権者から裁判を起こされて、判決などの債務名義を取られているような場合は、そこから時効が10年延長されます。
よって、貸金業者からの借金であっても、すでに債務名義を取られているような場合は時効が5年ではなく10年となりますが、そうでない限りは個人間の借金の半分の期間である5年で時効となります。
債権者が株式会社ではなく、信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構などの場合は、時効期間が10年となります。
これは、信用金庫などが営利を目的とした組織ではないからです。
ただし、信用金庫などからの借入れでも、債務者が個人事業主で事業目的で借入れをした場合は商事債権となるので、営利を目的としていない組織からの借入れであっても時効期間は5年となります。
※2020年(令和2年)4月1日以降に発生した債権については、改正民法の適用があるので、借入先にかかわらず時効期間は5年となります。
-
借金の時効はいつからスタートしますか?
-
借金の時効は最後に返済したときからスタートする
貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、時効期間がいつからスタートするかが問題です。
この点、消滅時効の起算点は期限の利益を喪失した日からです。
期限の利益喪失日というのは、債権者との契約に基づき、債務者が延滞をしたことによって分割払いをすることができなくなり、一括返済しなければいけなくなった日のことです。
よって、借主である債務者が分割払いを認められている間は時効が成立することはありません。
時効が成立しているかどうかの判断材料として、債権者から送付された催告書の中に「弁済期日」「約定返済日」などの記載がある場合は、その日付が5年以上前であれば、すでに時効期間が経過している可能性があるといえます。
-
5年が経過すると自動的に支払義務がなくなるのですか?
-
最後の返済から5年が経過しても自動的に時効が成立するわけではない
借金も5年で時効が成立しますが、たとえ最後の返済から5年が経過したからといって、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。
なぜなら、借主である債務者が自ら消滅時効の主張をしない限り、借金の支払義務がなくなることはないからです。
債務者が時効制度を知らないために消滅時効の主張(これを「時効の援用」といいます)をしなければ、たとえ、最後の返済から5年が経過していても、法的には借金の支払義務が残ったままとなります。
-
消滅時効を主張するにはどうすればいいですか?
-
配達証明付の内容証明郵便で通知するのが確実
たとえ最後の返済から5年が経過しても、借主である債務者が消滅時効を援用しない限り借金の支払義務はなくなりませんが、どのような方法で債権者に通知すればよいのかが問題となります。
消滅時効を援用する方法に特に決まりはありませんが、確実に証拠を残しておく意味でも口頭や普通の文書で通知するのではなく、配達証明付の内容証明郵便で消滅時効を援用するのが安全で最も確実な方法です。
なぜなら、内容証明で通知することで消滅時効を援用したことを証拠として残せるからです。
-
時効が更新する場合はどんな場合ですか?
-
債権者の請求と債務者の承認で時効は更新する
債権者の請求は、訴訟や支払督促などの裁判上の請求である必要があります。
よって、単なる文書での請求(一括請求の催告書、訴訟予告通知など)では時効は更新しません。
また、時効の更新とは一時停止という意味ではなく、それまで進行していた時効が一旦リセットされ、新たに時効がゼロからスタートするということです。
つまり、最後の返済から4年11ヶ月で時効が更新した場合、それまでの4年11ヶ月がゼロとなり、そこから新たに時効がスタートすることになります。
裁判外の請求であっても催告があった場合は時効の完成を6ヶ月だけ遅らせることができます。
これを「時効の完成猶予」といいます。
例えば、時効が完成する直前に内容証明郵便で債務者に催告し、その後6ヶ月以内に訴訟などの裁判上の請求をすれば時効は更新します。
債務者が借金を承認した場合も時効が更新します。
承認というのは借金の一部弁済のみならず、借主である債務者が貸主である債権者と支払方法について協議した場合(分割払いや減額のお願いなど)も含まれます。
時効期間経過後に債務の承認があった場合も時効は更新するので、債権者はすでに時効期間が経過している場合でも、時効の成立を阻止するために債務者の無知に乗じてあの手この手で借金を承認させようとしてきます。
-
数年ぶりに突然催告書が届いた場合はどうすればいいですか?
-
時効が成立している可能性があれば安易に連絡しない
途中で返済をやめてから数年が経ったにもかかわらず、ある日突然、債権者から借金の催告書が届く場合があります。
あわせて読みたい
すでに最後の返済から5年以上経過していることが明らかであれば、消滅時効の援用ができる可能性があるので安易に連絡をしてはいけません。
電話で借金の支払いについて話をしたり、減額のお願いをしてしまうと時効更新事由の債務の承認に該当する可能性があります。
ただし、形式的には債務の承認といえる返済に関する話をしてしまった後でも、消滅時効の援用ができる場合があるので、まずはご相談ください。
時効を更新させるには裁判上の請求である必要があるので、ご連絡のお願いや訴訟予告通知などの書面が届いただけでは時効は更新しません。
その意味でも、安易に債権者に電話をしてしまうと、相手のペースに乗せられて債務の承認をさせられる可能性があるので要注意です。
-
債権者が自宅に訪問してきた場合はどうすればいいですか?
-
一部弁済をせず借金の支払いについて一切の言質を与えない
5年の時効期間経過後であっても、債権者が突然自宅に訪問してくることがあります。
これは、時効期間経過後であっても、一部弁済などの債務の承認があれば時効が更新するからです。
そのため、債権者は突然、自宅などに訪問してきて「1000円でもいいから入金してください」等と言ってきます。
しかし、たとえ少額であっても一部弁済してしまうと時効が更新してしまうので、債権者が自宅に訪問してきた場合は借金の支払について一切の言質を与えないことが大切です。
債権者が時効を更新させる目的で、いきなり債務者の自宅を訪問し、債務者の無知に乗じて少額の一部弁済をさせた場合であっても、債務者の時効援用権は喪失しないという裁判例もあるので、一部弁済をした後でも時効の援用ができる場合があります。
-
債権者から訴えられた場合はどうすればいいですか?
-
5年の時効期間が経過していれば、裁判上で時効の援用をする
すでに時効期間が経過している場合でも、債権者が訴訟や支払督促を起こしてくることは珍しくありません。
なぜなら、裁判所は中立の立場なので、たとえ時効の援用が可能であっても、裁判所が被告である借主に時効の援用を積極的に促すことはないからです。
もし、被告である債務者が答弁書に分割払いを希望すると書いて裁判所に提出してしまうと債務の承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
よって、すでに時効期間が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用をしなければいけません。
具体的には答弁書を裁判所に提出して時効の援用をおこなう必要があります。
支払督促の場合は、支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。
訴状や支払督促が届いたにもかかわらず放置してした場合、たとえ時効期間が経過していても、債務者が時効の援用をしない限り、債権者の請求どおりの判決が出てしまうので、債権者から強制執行されるおそれがあります。
もし、ご自分で裁判をすることに不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない場合は、簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士に訴訟対応をお願いするのが安全です。
-
時効が成立しない場合はどうすればいいですか?
-
任意整理や自己破産を検討する
いまだ5年の時効期間が経過していなかったり、時効期間経過後に債務承認をしてしまい時効が更新してしまった場合は法的にも借金の支払義務があるので、消滅時効の援用をすることはできません。
そういった場合、定期的な収入があって分割返済することが可能であれば任意整理を検討し、返済できるだけの収入がないのであれば自己破産も視野に入れなければいけません。
どの手続きがベストであるかは当事務所にご相談ください。
-
債権回収会社から請求が来た場合の対処法は?
-
債権を譲り受けた会社に時効の援用をする
債権回収会社(サービサー)というのは、法務大臣の許可を受けた債権回収専門業者です。
長年返済がされていない債権は、当初の貸金業者が債権回収会社に債権を譲渡したり、回収業務を委託している場合が珍しくありません。
あわせて読みたい
債権譲渡があっても時効は更新しないので、例えば債権者Aから債権回収会社Bに債権譲渡されていても、最後の返済からすでに5年以上経過している場合は債務者は債権回収会社Bに対して消滅時効の援用ができます。
-
保証会社から請求が来た場合の対処法は?
-
代位弁済から5年以上経過していれば時効の援用ができる
銀行などの金融機関から借金をした場合、必ず保証会社が付いています。
その場合、債務者の返済が2~3ヶ月滞ると保証会社が代位弁済をして、債権者の地位が銀行から保証会社に移ります。
あわせて読みたい
保証会社は債務者の代わりに借金を返済することで、債務者に対して求償権を取得します。
これにより、代位弁済後は保証会社から請求を受けることになります。
しかし、求償権についても保証会社が代位弁済をした日から5年以上経過すれば時効の援用ができます。
よって、保証会社から請求書が届いた場合は「代位弁済日」から5年以上経過しているかどうかをチェックしてください。
-
保証人も時効の援用はできますか?
-
保証人も時効の援用ができる
すでに時効期間が経過している場合は、借入れをした主債務者だけではなく、保証人も消滅時効の援用をすることができます。
あわせて読みたい
ここでいう保証人は連帯保証人という意味です。
保証人がいる場合、債権者が主債務者に対して請求すると、保証人の時効も更新します(保証債務の附従性)。
よって、債権者が主債務者に対して裁判を起こして判決などの債務名義を取得した場合は、主債務のみならず連帯保証人の時効も10年延長されます。
また、債権者が保証人に対して請求すると主債務者の時効も更新します。
つまり、債権者はどちらか一方に請求をすることで両方の時効を更新させることができます。
これに対して、保証人が債務の承認をしても主債務者の時効は更新しないとされています。
なぜなら、主債務は保証債務に従属しないからです。
主債務者が債務承認をした場合は保証人の時効も更新します。
これに対して、例外的に時効期間経過「後」に主債務者が債務の承認をしても保証人の時効援用権は喪失しないとされています。
-
時効の援用をすることでブラックリストは消えますか?
-
時効の援用でブラックリストが消える
消滅時効の援用をすることで法的な支払義務はなくなります。
日本信用情報機構(JICC)の場合、加盟企業から消滅時効の援用があった旨の報告があるとファイルごと削除されて該当情報なし(ブラックリストが消える扱い)となります。
つまり、消滅時効の援用によって、ブラックリストがすぐ消えるわけです。
これに対して、シー・アイ・シー(CIC)の場合、加盟企業から消滅時効の援用があった場合は残高は「0」、終了状況は「完了」、「保有期限」には5年後の日付が記載されます。
ただし「返済状況」に登録された異動年月日はそのままです。
つまり、時効が成立しても異動情報が登録され続けて5年後にブラックリストが消えることになります。
あわせて読みたい
-
事故情報がない場合は時効の援用をする必要はないですか?
-
事故情報がなくても借金が残っている場合がある
借金を滞納している間は、原則的に信用情報機関に事故情報が掲載され続けます。
しかし、当初の債権者から債権回収会社などに債権譲渡された場合、信用情報には「移管終了」と記載されます。
債権を譲り受けた債権者は信用情報機関に加盟している貸金業者ではないので、CICでは債権譲渡から5年、JICCでは1年で元の信用情報自体を削除します。
そのため、債権回収会社などに譲渡された場合、借金自体は存在しているにもかかわらず、信用情報機関に事故情報が一切載っていないことがあるわけです。
よって、信用情報機関に照会したところ事故情報が一切載っていなかったとしても、借金自体がなくなったわけではないので、ある日突然債権回収会社から催告書が送られてきたり、裁判上の請求をされる場合があります。
-
消滅時効の援用後に借金がないことの証明書はもらえる?
-
借金がなくなったことの証明書はもらえないことが多い
消滅時効の援用をすることで法的には借金の支払義務がなくなります。
しかし、借金を完済したわけではないので、完済証明書を発行しなかったり、契約書の原本は返却してくれない債権者が圧倒的に多いのが実情です。
債権者の中には時効の援用によって契約が終了したとして、当初の原契約書を返却してきたり、債務不存在証明書、債権放棄額証明書などの書類を送ってくれるところもあります。
よって、借金がなくなったことの証明書は発行してもらえるかはケースバイケースです。
なお、消滅時効の援用は証拠を残すという点からも配達証明付の内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実です。
当事務所では時効援用後に内容証明と配達証明の控えを依頼者に交付しているので、それが消滅時効を援用したことの証拠となります。
-
奨学金にも時効はありますか?
-
奨学金も10年で時効になる
日本学生支援機構(旧育英会)などの奨学金も、返済期日から10年が経過すれば消滅時効の援用が可能です。
奨学金の時効の起算点については、各回の返済期日から個別に進行するとされています。
近年、日本学生支援機構は滞納奨学金の回収に力を入れているため、債権回収業務を三菱HCキャピタル債権回収、アルファ債権回収といった債権回収会社に委託しています。
あわせて読みたい
そのため、長期間にわたって奨学金を滞納している場合は債権回収会社から催告書が届いたり、裁判所から訴状や支払督促が送付されることがあります。
なかには、10年の時効期間が経過している場合があり、そういったケースでは更新事由がない限りは時効の援用ができます。
-
携帯料金にも時効はありますか?
-
携帯料金は5年で時効になる
ドコモ、au(KDDI)、ソフトバンク(旧ウィルコム)などの携帯電話の利用料金も、サラ金やカード会社の借金と同じように5年で時効となります。
あわせて読みたい
ただし、時効期間が経過する前に携帯会社から訴訟や支払督促などの裁判上の請求を受けた場合は、時効が10年に延長されます。
大手3社の中ではドコモが最も回収に力を入れている印象があります。
ドコモ、ソフトバンクは自社で請求するだけではなく、回収業務をニッテレ債権回収などの債権回収会社に委託している場合もあります。
あわせて読みたい
携帯電話の端末料金を利用料金と一緒に分割で支払っている場合は、契約上は商品の分割払いをしていることになります。
その場合、毎月の利用料金の返済が滞ると携帯会社が加盟しているシー・アイー・シー(CIC)に事故情報が掲載されてしまい、信用情報がいわゆるブラックとなります。
よって、端末料金を含んだ携帯料金を滞納している場合は、たとえ消滅時効の援用ができたとしても、その後、5年間は信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が載ることになるので注意が必要です。
-
遠方からでも依頼することはできますか?
-
内容証明郵便の作成のみであれば可能です
消滅時効の援用は任意整理業務に含まれますが、司法書士が顧客から依頼を受ける場合は原則的に本人との面談が必要になります。
よって、お客様が遠方の場合は当事務所までご来所頂けるかどうかがポイントとなります。
当事務所へのご来所は原則的に契約時の一度だけでOKで、その後は、電話、LINE、メール、郵便ですべてのやり取りが可能です。
これに対して、遠方の方で当事務所までお越し頂くことができない方は内容証明作成サービスをご利用ください。
よって、遠方の方で当事務所までお越し頂けない方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数8000人以上
-
お願いした場合の費用はいくらですか?
-
消滅時効の援用は1社あたり5万円です
消滅時効の援用は任意整理の報酬が適用されます。
当事務所の任意整理報酬は1社あたり5万円(税抜き)です。
消滅時効の援用の場合、この他に実費として内容証明郵便の料金がかかります。
具体例を挙げて説明しますと、債権者1社のみの依頼の場合、消費税と郵便料金を含めた総額は5万6645円となります。
時効が成立しても成功報酬は一切かかりませんのでご安心ください。
遠方の方で当事務所までお越しいただけない場合の内容証明作成サービスの料金は1社あたり3万円(税抜き)となっており、こちらは一括前払いのみでの対応となりますのでご了承ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。
債権回収会社や弁護士事務所などから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
最新の投稿
- 2025年8月6日三菱HCキャピタル債権回収株式会社の時効援用
- 2025年8月5日エイワの取り立てと裁判や支払督促の時効援用
- 2025年8月4日沖縄債権回収サービス(おきなわサービサー)の時効援用
- 2025年1月14日0120309845のプライメックスキャピタル(キャスコ)の時効援用