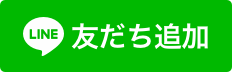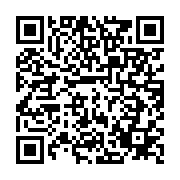公開日: 2017年12月11日 | 最終更新日:2024年1月18日
過払い金とは?返還請求のやり方や流れ、各社の対応など
- 1. 過払い金とは?返還請求のやり方や流れ、各社の対応など
- 1.1. 利息制限法とは
- 1.2. みなし弁済とは
- 1.3. 過払い金返還請求とは
- 1.4. 過払い金の利息
- 1.5. 過払い金の消滅時効
- 1.6. 完済後の過払い請求
- 1.7. 過払い金の充当について
- 1.8. 過払い請求とブラックリスト
- 1.9. 過払い金請求は専門家にお願いするのが安全
- 1.10. 過払い金返還請求の流れ
- 1.11. 取引履歴の開示請求
- 1.12. 取引履歴の再現と引き直し計算
- 1.13. 訴訟による過払い金の回収
- 1.14. 訴訟提起後の問題点
- 1.15. 訴訟外での和解交渉
- 1.16. 過払い請求の対応
- 1.17. 過払い請求、各社の対応
- 1.17.1. アイフル
- 1.17.2. アコム
- 1.17.3. アプラス
- 1.17.4. アペンタクル(ワイド)
- 1.17.5. イオンクレジットサービス
- 1.17.6. SFコーポレーション(三和ファイナンス)
- 1.17.7. エイワ
- 1.17.8. エポスカード
- 1.17.9. NISグループ(ニッシン)
- 1.17.10. オリエントコーポレーション
- 1.17.11. クレディセゾン
- 1.17.12. JCB(ジェーシービー)
- 1.17.13. ワイジェイカード
- 1.17.14. 新生フィナンシャル(レイク)
- 1.17.15. 新生パーソナルローン(シンキ)
- 1.17.16. CFJ(アイク、ディック、ユニマット)
- 1.17.17. セゾンファンデックス
- 1.17.18. セディナ
- 1.17.19. ゼロファースト
- 1.17.20. 三菱UFJニコス
- 1.17.21. ニッセンジーイークレジット
- 1.17.22. ネオラインキャピタル
- 1.17.23. プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)
- 1.17.24. ライフカード
- 1.17.25. 日本保証(武富士)
利息制限法とは
10年くらい前からテレビやラジオCM、折り込みチラシなどで過払い金請求という言葉を耳にするようになったと思いますが、ここでは、この過払い金が発生する仕組みを分かりやすく解説したいと思います。
利息制限法では、制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。
しかし、10年以上前のサラ金業者やカード会社の多くが、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしていました。
利息制限の他に出資法という法律もあり、この法律では上限利率を年29.2%としています。
では、この2つの法律の関係はいったいどうなっているのでしょうか?
例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。
利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。
しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。
この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資していました。
みなし弁済とは
もう一つ知っておいてもらいたいものでみなし弁済規定というものがあります。
利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。
ですから、サラ金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくありません。
このみなし弁済規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、貸金業者のほとんどがこの要件をすべてきちんと満たしていることはほとんどないと言っていいでしょう。
貸金業者がグレーゾーン金利の正当性をみなし弁済規定により主張するには、厳格な要件を満たしていることを主張・立証する必要があります。
この要件を業者が満たしていない場合はみなし弁済の適用はなく、業者が主張するグレーゾーン金利は利息制限法に引き直しされるべきです。
過払い金返還請求とは
-
過払い金とは何ですか?
-
過払い金といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理をしている弁護士・司法書士の間では10年以上前から盛んに過払い金の回収がおこなわれています。
この過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
-
元本の金額が増減した場合に適用される利率は何%ですか?
-
なぜ、過払い金が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
-
どのくらいの取引で過払い金は発生しますか?
-
過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引き直し計算をしてみる必要があります。
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。
一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。
-
過払い金回収を自分ですることはできますか?
-
過払い金返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。
しかし、現実的には弁護士・司法書士に依頼しないで自分で過払い金を回収しようと思っても、貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないことが多いと思います。
そうなりますと債務者は裁判を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要になるのでかなりの困難を伴うことになります。
そういった事情を考慮しますとやはり弁護士・司法書士に依頼をするのが無難といえるでしょう。
過払い金の利息
-
過払い金に利息は発生しますか?
-
過払い金には5%の利息が発生します(最高裁平成19年2月13日判決)。
この判決は「商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払い金を不当利得して返還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当である」と述べています。
この利息は過払い金の発生時から発生します(最高裁平成21年9月4日判決)。
-
悪意の受益者とはなんですか?
-
民法704条の規定する利息は「悪意の受益者」に対してのみ請求できます。
ここでいう「悪意」というのは、法律上の原因がない不当利得であることを知っている(認識している)という意味であって、「悪質な」「悪徳な」等といった意味ではありません。
-
貸金業者が悪意の受益者であること立証するにはどうすればいいですか?
-
最高裁平成19年7月13日、同7月17日判決は、貸金業者であれば貸金業法43条1項のみなし弁済規定の適用がない場合、発生した過払い金を不当利得して借主に返還しなければいけないことは十分に認識していることから、貸金業者においてみなし弁済規定の「適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情」がなければ、民法704条の悪意の受益者であることが推定されると判示しました。
よって、貸金業者の側においてみなし弁済の立証ができなければ、みなし弁済が成立しないだけでなく、悪意の受益者であることが推定され、貸金業者においてこの推定を覆す特段の事情を立証しない限り、悪意の受益者として、5%の利息が過払い金に付加されることになります。
過払い金の消滅時効
-
平成15年に完済した分の過払い金は今からでも回収できますか?
-
過払い金返還請求権を言い換えれば「不当利得返還請求権」となります。
そして、この不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
-
消滅時効はいつから進行しますか?
-
過払い金返還請求権の消滅時効は10年ですが、それがいつから進行するのかが問題となります。
今までは、取引終了時から進行するという「取引終了時説」と、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという「個別進行説」が対立していました。
しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判決が相次いで出たことにより決着しました(最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決)。
-
平成25年に完済した分の過払い金は今からでも回収できますか?
-
過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から10年なので、平成30年に取引が終了したのであれば令和10年までは過払い金返還請求が可能となります。
しかし、取引終了時点が平成30年ではなく平成20年の場合は、取引終了からすでに10年が経過していますので消滅時効にかかります。
完済後の過払い請求
-
完済すれば必ず過払い金が発生するのですか?
-
完済したからといって、必ず過払い金が発生するわけではありません。
過払い金が発生するには、金利が利息制限法を超えていることが条件となります。
たとえば、金利18%で50万円の借入れをし、その後、5年かけて完済したとします。
この場合、利息制限法の上限金利は18%なので、たとえ完済しても過払い金は発生しません。
これに対して、金利が18%を超えていたのであれば違法金利なので、完済した以上は確実に過払い金が発生していることになります。
-
完済してから5年以上が経過していますが過払い請求できますか?
-
過払い金の消滅時効は10年で、その起算日は取引終了時点となります(最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決)。
よって、取引が終了してから10年以内であれば過払い請求可能です。
-
完済した際に契約書や領収書を捨ててしまったのですが、過払い請求できますか?
-
通常、借入当時の契約書や領収書は完済すれば捨ててしまうものです。
そのため、契約書等が残っていないと過払い請求ができないと勘違いされている方が多いです。
しかし、借入れをしてから完済をするまでの取引履歴は貸金業者が保存しているので、借りた貸金業者名さえ分かれば、過払い金を回収できる可能性があります。
-
完済後の過払い請求でもブラックリストに載ってしますのですか?
-
完済した貸金業者に対する過払い請求であれば、ブラックリストに載ることはありません。
ただし、過払い請求をした直接の相手業者からは借入れをすることができなくなります。
-
完済してから今に至るまでの利息を含めて過払い請求できますか?
-
貸金業者が悪意の受益者である場合には、過払い金に5%の利息を付けて請求することができます。
完済時点で100万円の過払い金が発生していれば、1年あたり5万円の利息がつくことになります。
よって、5年前に完済していれば125万円(元金100万円、利息25万円)を過払い請求できることになります。
過払い金の充当について
-
借入金を一度完済して、期間をおいて再度借入した場合でも一連計算できますか?
-
完済したことにより発生した過払い金を新たな借入金債務に充当できるかどうかは借入れが基本契約に基づく場合と基本契約が締結されていない個別契約(証書貸付け)の場合で異なります。
そこで、以下では最初の借入れから債務をいったん全額返済するまでの取引を第1取引、新たな借入れを第2取引として4つのパターンに分けて解説します。
-
第1取引開始時に基本契約を締結し、その基本契約が第1取引および第2取引を通じて1個の場合の過払い金の充当は?
-
最高裁平成19年6月7日判決は、借入金額・返済方法・返済金額、利息の計算方法が定められた基本契約が締結されている場合は、借入限度枠の範囲で繰り返し借入れをすることができ、債務の弁済は借入金全体に対して行われるものであり、基本契約は「弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる」と判示しました。
つまり、基本契約が1個であれば、途中で何年の空白期間があっても一連計算できるということになります。
この判決が示した基本契約にはクレジットカード契約はもちろん、ほとんどすべてのサラ金の借入限度契約が該当します。
-
第1取引と第2取引開始時にそれぞれ基本契約を締結した場合(基本契約が2個以上ある場合)の過払い金の充当は?
-
最高裁平成20年1月18日判決は、第1取引の債務を完済して過払い金が発生し、その後新たな借入れをするにあたって第2取引の基本契約が締結された場合、新たな借入金債務に過払い金は当然に充当されないと判示しました。
しかし、同判決では過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなどの特段の事情があれば過払い金は新たな借入金債務に充当されるとも述べています。
取引の途中で基本契約書が何回か作成されていても、取引に空白期間がなく前後で取引が途切れていなければ、いわゆる契約の「切替え」にすぎず、基本契約の内容を変更しただけなので1個の貸付取引であるといえます。
よって、基本契約が数回締結されていても、それが契約の切替えに過ぎない場合は一連計算できることになります。
-
充当が認められる特段の事情とは何ですか?
-
充当が認められる特段の事情とは何ですか?
最高裁平成20年1月18日判決で示された過払い金の充当の合意等が存在することの特段の事情を判断する事項は以下のとおりです。
同判決では特段の事情を判断するための材料は示されたのですが、貸主と借主の間で過払い金の額に争いがあるために和解に至らなければ、結局のところ借主が貸主に対して過払い金返還請求訴訟を起こす必要があり、訴訟をしてもなお和解に至らないのであれば、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。
充当が認められる特段の事情
【1】 第1取引の基本契約に基づく取引期間の長さや第2取引の基本契約までの空白期間の長さ
【2】 第1取引の基本契約の契約書の返還の有無
【3】 ATMカードの失効手続の有無
【4】 空白期間における貸主と借主との接触の状況
【5】 第2取引の基本契約が締結されるに至る経緯
【6】 第1取引と第2取引の各基本契約における利率等の契約条件の異同
【7】 その他等
-
基本契約は締結されていないが借入れが反復・継続している場合の過払い金の充当は?
-
最高裁平成19年7月19日判決は、基本契約が締結されていない個別契約(証書貸付け)で複数の貸付けが行われた場合、各貸付は「貸付けの切替え及び貸増しとして、長年にわたり同様の方法で反復継続して行われていたもの」で1個の連続した貸付取引であり、このような場合は、当事者は一つの貸付けを行う際に、次の貸付けを行うことを想定しており、複数の権利関係が発生するような事態(第1取引の過払い金が第2取引の貸付けに充当されずに残ってしまう事態)が生ずることを望まないのが通常であることから、過払い金を「新たな借入金債務に充当することを合意している」と判示しました。
つまり、個別契約(証書貸付け)の場合でも借入れが反復・継続している場合は一連計算できることになります。
この判決では途中で約3ヶ月半の取引の中断がありましたが一連計算が認められました。
-
基本契約が締結されておらず、借入れも反復・継続していない場合の過払い金の充当は?
-
最高裁平成19年2月13日判決は、基本契約が締結されず、消費貸借契約が2系列ある事案において、一つの貸付けに際して、第2取引の貸付けを想定していたとか「過払い金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り」過払い金は新たな貸付金債務に充当されないと判示しました。
しかし、この判決では充当の特約に加え、基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返され、第1の貸付けの際に第2の貸付けが想定されるというなどの特段の事情があれば充当されるとも述べていますので、決して充当の道を閉ざすような判決ではありません。
この判決は2つの証書貸付けによる取引が同時並行している事例であり、貸付取引が1系列であるケースには適用されません。
過払い請求とブラックリスト
-
ブラックリストとは何ですか?
-
ブラックリストとは、民間の信用情報機関が個人の信用情報を収集して作成しているデータベース(名簿)のことをいいますが「ブラックリスト」という名称のデータベースがあるわけではありません。
あわせて読みたい
-
指定信用情報機関とは何ですか?
-
指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人であり、一定の要件を満たすことを条件に内閣総理大臣により指定される機関であり、個人情報の保護に関する法律を遵守する必要があります。
改正貸金業法により、信用情報機関はよりいっそう厳格に情報を管理し、過剰貸付を防止するための役割を担うことになりました。
ここでは主なものを3つ紹介します。
これらの指定信用情報機関は取引を開始する際の個人の経済的信用力(返済能力)を調査するのが目的です。
指定信用情報機関
- 日本信用情報機構(JICC) ※サラ金・信販系
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC) ※信販会社・クレジット会社系
- 全国銀行個人情報信用センター(KSC) ※銀行系
-
事故情報とはどういった内容のものですか?
-
事故情報の主なものに【1】借主の「延滞」の事実、【2】弁護士・司法書士による「債務整理」が始まった事実、【3】借主に代わって保証会社が「代位弁済」した事実、【4】「破産」「個人再生」「特定調停」の申立ての事実があります。
【1】の「延滞」の場合、借主が貸主に対する支払いを怠り、61日以上または3か月以上経過した場合に貸主の申告により登録されますが、期間は信用情報機関により異なります。
-
ブラックリストに載ると一生借り入れができなくなるの?
-
いわゆるブラックリストに載ってしまっても、貸金業者との取引が終了してからおよそ5~10年が経過すると事故情報を含めて個人信用情報は削除されますので、一生ローンを組んだり、カードを作ることができないというわけではありません。
-
ブラックリストに載るとブラックリストに載ると一生借り入れができなくなるの?
-
ブラックリストに載ると新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品を購入することができなくなります。
よく、ブラックリストに載った事実が住民票や戸籍に記載されるのではないか、国民健康保険や民間の生命保険に加入できなくなるのではないか、国民年金の支払いがされなくなるのではないか、などと質問されますがそんなことはありません。
賃貸契約にも影響はありませんがクレジットカードを利用して家賃を支払う必要がある場合は、新規の賃貸契約が締結できない可能性はあります。
すでに組んでいる自動車ローンは、そのローンの支払いが滞らない限り、たとえブラックリストに載っても自動車がローン会社に引き揚げられることはありません。
このようにブラックリストに載るとお金が借りられなくなったり、カードを利用することはできなくなりますが、それ以外の日常生活にはほとんど影響はありません。
-
負債が残っている債権者に対して過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまうのですか?
-
これには2つのケースが考えられます。
まずは、利息制限法で引き直し計算をしても負債が残る場合。
引き直し後の負債を無利息で分割返済すれば(これを任意整理といいます)、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録されてしまいます。
あわせて読みたい
次は、利息制限法で引き直し計算をすればすでに過払いであった場合。
これについては株式会社日本信用情報機構が平成22年4月19日からサービス情報71「契約見直し」の収集・提供を廃止することになりました。
同社によると「平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止し」「既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除」するとのことです。
つまり、現時点で負債が残っていても、利息制限法で引き直しをすればすでに過払いの場合は、業者に過払い請求をしても今までのように「契約見直し」とはならない(いわゆるブラックリストに載らない)ことになりました。
サービス情報71「契約見直し」とは
加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報のこと
-
完済をした債権者に対して過払い金返還請求をしてもブラックリストに載ってしまうのですか?
-
この場合はブラックリストに載ることはありません。
過払い金請求は専門家にお願いするのが安全
借主側が裁判外で利息制限法による引き直し計算を根拠にした金額を主張したとしても、業者側が素直に認めることはまずないと言っていいでしょう。
ですから、実際にグレーゾーン金利を利息制限法で引き直し計算をするには司法書士や弁護士に介入してもらうか、裁判上の手続きを取る必要があります。
これにより利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入れられることになり、元金が大幅に減少し、場合によっては過払いになっていることもあります。
過払い金が発生していることが判明した場合は、司法書士や弁護士に過払い金返還請求の手続をしてもらう必要があります。
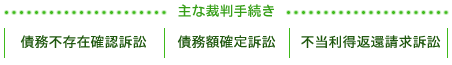
過払い金返還請求の流れ
司法書士などの専門家に過払い金返還請求を依頼すると、以下のような手順となります。
- 1:貸金業者への受任通知の発送
- 受任通知が届いてからおよそ1~2か月程度で貸金業者から取引履歴が届きます
- 2:利息制限法による引き直し計算
- 高金利で借入れをしていた場合は利息制限法で再計算して過払い金額を算出します
- 3:貸金業者への過払い金返還請求
- 任意の交渉で満額和解になることはほとんどないので、当事務所では原則的にすぐに提訴します
- 4:和解成立
- 手続開始から入金までの標準期間は3か月~半年程度です
返金時期は相手業者によってかなり異なりますが、早いところだと手続開始から3か月程度で回収できることもあります。
しかし、近年は大手の貸金業者といえども経営状態が悪化しているため、提訴しても回収までに半年程度かかることが多く、裁判が長期化した場合は1年近くかかることがあります。
中小の貸金業者だと判決を取っても回収できないところが増えています。
取引履歴の開示請求
-
取引履歴の開示請求はどのようにすればよいのですか?
-
貸金業者に取引履歴の開示を求める場合は電話ではなく、普通(書留)郵便、内容証明郵便、FAX等の文書で請求するのがよいでしょう。
文書で請求をしておけば、訴訟になった場合でも取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をする際の証拠として使えます。
文書で通知をする際には仮に自己破産や個人再生になる見込みが高い場合でも、単に債務整理をする旨を記載しておきます。
はじめから自己破産である旨を記載してしまうと残高のみを通知してきて取引履歴を開示しない貸金業者もいるからです。
-
貸金業者が取引履歴の一部しか開示しない場合はどうすればいいですか?
-
貸金業者に取引履歴の開示を請求しても一部(3年~10年)しか開示されない場合があります。
その際の業者の言い分には①社内規定上出せない、②10年以上前の取引記録は随時廃棄処分している、等といったものがあります。
このように一部の取引履歴しか開示してもらえない場合、まずは監督庁(各地の財務局、都道府県金融課等)に行政指導をしてもらうように上申します。
貸金業者も監督庁からの指導があれば取引履歴を開示する場合することがあります。
ただし、貸金業者の中には行政指導があっても一切開示をしないところもありますし、既に10年間の取引履歴が開示されているような場合は監督庁も行政指導をしません。
よって、監督庁に行政指導の申出をしても開示されないようであれば訴訟を提起するほかありません。
-
貸金業者が0円和解を要求してきた場合はどうすればいいですか?
-
貸金業者に取引履歴の開示を請求すると履歴の開示をすることなく貸金業者から債権債務なしで和解をしませんか(これを『0円和解』といいます)、と言われることがあります。
貸金業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してくるということは過払い金が発生していると考えてまず間違いありません。
仮に、債務が残っているとすれば貸金業者が0円和解を提案することはありません。
0円和解をするかどうかは取引履歴の開示を受けたうえで利息制限法の引き直し計算をして過払い金がいくらになるのかを確かめる必要があります。
ですから、安易に0円和解をするべきではないといえます。
取引履歴の再現と引き直し計算
-
引き直し計算はどのようにすればいいのですか?
-
貸金業者から取引履歴を開示してもらったとして、その計算書が貸金業者の約定利率に基づくもので利息制限法を越えた利率での貸付けの場合は債務者自身が引き直し計算をする必要があります。
引き直し計算といってもどのようにすればよいか分からない方がほとんどだと思いますが、最近ではインターネット上から引き直し計算の専用ソフトをダウンロードできるのでそれらを利用したり、過払い金専門の書籍に付いているCD-ROMを利用するのが簡単です。
これらのソフトを利用すれば日付と借入金額・返済金額を入力すればあとはソフトが自動計算してくれます。
-
元本の金額が増減した場合に適用される利率は何%ですか?
-
利息制限法で定められている上限利率は以下のとおりです。
貸金業者と基本契約を締結する場合は『極度額』や『借入限度額』が設定されるのが通常です。
利息制限法所定の利率を定める場合の元本はこの極度額または借入限度額を基準にします。
例えば、借入限度額が100万円の包括契約を締結した場合は実際に借り入れた金額が100万円未満であっても利率は15%となります。
最初に150万円を借りてその後に返済を続けた結果、残元本が100万円未満になっても利率は18%に上がることなく15%のままとなります。
極度額や借入限度額が定められていない個別契約の場合は、元本が10万円未満から10万円以上になれば利率も20%から18%になり、100万円以上になれば18%から15%になります。

-
過払い金に対して利息は発生するのですか?
-
過払い金にも利息は発生します。
過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。
過払い金の利息は5%(民法404条)です。
貸金業者に過払い金を請求する段階で利息も請求しておけば、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうといった条件を提示できます。
よって、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。
-
借換えや再借入れがある場合はどのように計算すればいいのですか?
-
借換えというのは、例えば取引の途中で新たな貸付けをすると同時に旧債務の残額をゼロとして新たな借入れから旧債務の元本・未払い利息を差し引いた差額の現金を交付することです。
再借入れというのは、貸金業者の定める約定利率でも借入金を完済して(引き直し計算をすれば過払い金が発生しています)、一定期間が経過した後に再び借入れをすることです。
このような借換えや再借入れといった事情があっても引き直し計算をする際は一連の取引として単純に計算をすればよいでしょう。
-
貸金業者が取引履歴を開示しない場合の引き直し計算の方法は?
-
貸金業者によってはどんなに取引履歴の開示請求をしても応じてくれないところがあります。
そのような場合は訴訟を提起するほかありませんが、その場合に取引履歴を自分で再現する必要があります。
これを推定計算といいます。
推定計算をする場合、手元に貸金業者との契約書や領収書がすべて残っていればそれに基づいて引き直し計算をすればいいのですが、そのような書類が残っているのは非常に稀であり、たいていの場合は債務者の記憶に基づいて引き直し計算をすることになります。
記憶に基づいて推定計算をする場合にどの程度正確でなければならないかといった問題がありますが、それほど正確である必要はありません。
取引開始日の数年のずれや返済日の数日のずれ、数万円の返済金額のずれがあっても問題ありません。
取引履歴が事実と異なっていてそれが貸金業者にとって不利な内容であれば貸金業者から指摘があるはずなので適宜直せばいいでしょう。
本当の過払い金額よりも推定金額の方が少ないと業者が推定計算をすんなりと受け入れてしまいますので、推定計算をする場合は実際の過払い金額よりも多くなるようにしておくべきです。
訴訟による過払い金の回収
-
簡易裁判所と地方裁判所のどちらに提起すればいいのですか?
-
簡易裁判所か地方裁判所のどちらに提起するべきかは訴額がいくらかによって決まります。
といいますのも、民事訴訟法では訴額が140万円以下の場合には「簡易」裁判所、140万円を越える場合には「地方」裁判所と決められているからです(これを事物管轄といいます)。
訴額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、これには請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。
-
訴訟は自分の住んでいる近くの裁判所に提起すればいいのですか?
-
過払い金の返還債務は持参債務(原告である債務者の住所地で支払うべき債務)ですから、過払い金返還請求訴訟は原告である債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができます。
ただし、貸金業者が交付する契約書には通常、訴訟になった際の管轄の合意として『貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します』等とあらかじめ書かれています。
現在ではこのような約款による管轄の合意は無効であると考えられています。
仮に有効だとしても専属的合意管轄(その裁判所のみを管轄裁判所とする合意)ではなく、競合的管轄合意であると考えるべきですので原告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することができます。
-
弁護士費用や慰謝料の請求を上乗せすることはできますか?
-
過払い金返還請求訴訟を提起する際に弁護士費用や取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をすること自体は自由です。
ただし、認められるかどうかはケースバイケースといえるでしょう。
貸金業者の取引履歴の不開示が違法行為であると評価されるためには少なくても文書で3回、口頭で3回以上は請求する必要があると思われます。
このような債務者からの再三の請求にもかかわらず長期にわたって開示を拒んだような場合には取引履歴の不開示による損害賠償請求が認められる可能性が高くなります。
弁護士費用の目安は10万円程度、慰謝料の目安は10~30万円程度です。
-
契約書や領収書がない場合でも訴訟を提起することはできますか?
-
契約書は領収書等がなくても訴訟を提起することか十分可能です。
貸金業者から取引履歴が開示されず推定計算に基づいて訴訟を提起したような場合は、訴訟の中で貸金業者に取引履歴を開示させて請求金額を確定すればいいでしょう。
契約書等の書類がすべて残っていたり、通帳に借入れと返済の記録が残っているような場合は貸金業者から取引履歴の開示がなくてもそれらの書類に基づいて取引履歴を再現することになります。
-
貸金業者が合併をしている場合はどうすればいいですか?
-
貸金業者の中には合併を繰り返している会社も少なくありません。
会社が合併した場合、債権と債務のすべてが合併後の新会社に包括的に承継されるので合併前の会社が負っていた過払い金返還債務も新会社が承継することになります。
よって、合併後の貸金業者に対して過払い金の返還請求ができます。
訴訟提起後の問題点
-
貸金業者から移送の申立てをされた場合はどうすればいいですか?
-
過払い金返還請求訴訟は債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができますが、貸金業者が契約書の合意管轄等を理由に本社の住所地のある裁判所に移送申立てをすることがあります。
このような移送申立てがあった場合は裁判所に反論書(意見書)を提出する必要があります。
意見書を提出したにもかかわらず貸金業者の主張が認められてしまった場合は移送の決定書を受け取ってから1週間以内に即時抗告の申立てをすることができます。
即時抗告を棄却した決定に対しては再抗告することができるので最後まで諦めないようにしましょう。
-
訴訟提起後に請求金額を訂正することはできますか?
-
貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算により訴訟を提起することになりますが、訴訟提起後に開示された取引履歴に基づいて引き直し計算をした結果、訴状に記載した請求金額が実際の過払い金額と食い違うことになります。
訴状の請求金額よりも実際の過払い金額が多額になった場合は訴えの変更をして請求を拡張する必要があり、この場合は追加の印紙代が必要となります。
逆に訴状の請求金額が実際の過払い金よりも高かった場合、請求金額を減少することになり、法的には訴えの一部を取下げることになります。
-
訴訟提起後に訴えを取り下げることはできますか?
-
仮に過払い金返還請求訴訟を提起したとしても訴訟外で貸金業者と和解を締結することは珍しくありません。
そうなった場合は訴えの取下げをする必要があります。
第1回の口頭弁論の期日前であれば原告である債務者が訴えの取下書を裁判所に提出すれば訴えを取下げることができます。
第1回の期日以降の取下げの場合は被告である貸金業者の同意が必要になりますので貸金業者に和解書とともに取下書を送ってゴム印と社判をおしてもらいそれを裁判所に提出することになります。
第1回期日前に訴えを取り下げた場合は印紙代金の一部を返還してもらうことができますが、自動的に戻ってくるわけではないので訴えを提起した裁判所に手数料還付の申立てをする必要があります。
-
貸金業者がみなし弁済を主張してきた場合はどうすればいいですか?
-
過払い金返還請求訴訟を提起すると貸金業者からみなし弁済を主張されることがあります。
ただし、みなし弁済が認められるためには貸金業者は厳格な要件を満たす必要がありますので、みなし弁済が認められることはないと考えていいでしょう。
貸金業者が債務者の無知に乗じてみなし弁済を認めることを前提とした和解契約を締結していたとしても利息制限法を超過する利息の約定は無効です。
訴訟外での和解交渉
-
過払い金の返還請求はどのように通知すればよいのでしょうか?
-
過払い金が発生していることがわかった場合、貸金業者にその返還を求めることになりますが、その際は電話ではなく文書(内容証明郵便、書留、FAX等)でする必要があります。
内容証明郵便であればそれ自体が証拠になりますが、FAXで通知する場合は送信記録を保存しておいたほうがいいでしょう。
-
裁判をしないと過払い金は回収できないのでしょうか?
-
貸金業者にもよりますが、裁判外で過払い金の返還に応じてくれるところもあります。
ですから、訴訟をしないと過払い金を回収できないというわけではありません。
ただし、その場合には過払い金の3割~9割程度減額した金額で和解をすることが多いのが実情です。
どの程度の減額であれば和解をするべきかについては債務者本人の判断によります。
もし、減額を一切したくない場合や貸金業者が過払い金の返還に応じてくれない場合は訴訟を提起するのがいいでしょう。
-
貸金業者からの減額の申出は受けるべきでしょうか?
-
貸金業者に対して訴訟外で過払い金の返還請求をするとほとんどの場合、減額を要求してきます。
この減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、仮に訴訟となれば圧倒的に貸金業者側が不利なので安易に減額要求に応じる必要はありません。
多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をした方がいい場合としては、過払い金を他の債権者への返済に充てるなどの事情がある場合です。
特に過払い金を早期に必要としないのであればじっくりと腰を据えて強気の交渉をするべきでしょう。
-
一度、和解をした後に過払い金返還請求をすることはできますか?
-
例えば、一度、貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を越えた利率)を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を貸金業者と締結していたとしても、利息制限法で引き直し計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は過払い金の返還請求をすることができます。
なぜなら、利息制限法を超過する利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。
過払い請求の対応
過払い金返還請求をするには、まず、相手業者から取引履歴を取り寄せて、引き直し計算をする必要があります。
引き直し計算の結果、過払い金が発生していれば、相手業者に対して返還請求をすることになります。
過払い金請求がおこなわれるようになった平成18年から数年間はFAXや電話で交渉をすれば、過払い元金の全額~8割程度であれば和解に応じる業者が多かったです。
しかし、近年では過払い元金の半分程度でないと和解に応じない業者がほとんどなので、過払い元金全額やそれ以上(過払い利息を含めた満額)を回収するには裁判(過払い金返還請求訴訟)を起こす必要があります。
裁判を起こしたからといってすぐに満額の返金に応じてくれるというわけではなく、過払い利息(実務上は「悪意の受益者」といいます)については、争ってくる業者がほとんどです。
実際に過払い金を回収できるまでの期間は業者によってかなり異なるのが実情です。
そこで、当サイトで各社の過払い請求の対応を掲載することにしましたので、皆様の参考になれば幸いです。
ただし、直近の各業者の対応を保証するものではありません。
過払い請求に対する業者の対応は、司法書士等の専門家に依頼をしないでご本人でおこなう場合と、専門家がおこなう場合とでかなり異なります。
同じ専門家でも事務所によって対応を変える業者もありますし、業者の対応は一日で変わることもありますので、同じ業者であっても必ずしも掲載内容と一致するというわけではありませんのでご了承下さい。
過払い請求、各社の対応
アイフル
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割以下。
訴訟をしても5割以上での和解は困難なので、5割以上回収したい場合は判決を取る必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
判決後にアイフルが控訴してこなければ4ヵ月~半年前後。
控訴してきた場合は半年から10ヵ月前後。
※当事務所では原則的に判決を取るため、和解した場合の返金時期は分かりませんが数ヶ月だと思われます。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
ただし、第一審で判決を取っても、アイフルが控訴してくることがあります。
判決を取った場合、返還日までの過払い利息を付加した過払い金全額が返金されます。
注意点
アイフルはアコムやプロミスのようにメガバンクの傘下に入っていないため、資金繰りが非常に厳しく、平成21年に「事業再生ADR手続」を申請しました。
今後も予断を許さない状況が続くと予想され、最終的には平成22年に破綻した武富士のようになる可能性があるので注意が必要です。
そのため、過払い元金の5~7割に減額してでも早期に和解するか、時間はかかっても判決を取り、過払い利息まで含めた過払い金全額の回収を目指すのか、正直判断が難しいところです。
司法書士には簡易裁判所までの訴訟代理権しかないため、簡易裁判所で判決を取っても控訴された場合、地方裁判所での本人訴訟となります。
しかし、控訴審は書面だけ提出すれば、依頼者本人が裁判所に出廷しなくて済む場合がほとんどです(実際に、当事務所の依頼者で控訴審に出廷して頂いたケースはありません)。
アコム
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割程度。
訴訟をすれば返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
ただし、過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は地方裁判所での本人訴訟となります。
本人訴訟の場合、必然的に過払い金額が大きくなりますので、過払い利息を含めた全額を回収しようとすると、弁護士を選任して争ってくる場合があります。
ただし、本人訴訟の場合でも、過払い元金全額に多少の過払い利息を含めた程度の金額であれば、依頼者本人が裁判所に出廷する前に和解になることがほとんどです。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から半年前後。
※ アコムも財務状況が悪化しており、今まで以上に入金までの期間が長くなってきており、現在はおおむね和解後3ヵ月の入金となります。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額で和解します。
過払い元金が140万円を超える本人訴訟の場合、過払い元金+αで和解し、依頼者本人は裁判所に出廷しないで済むケースが多いです。
注意点
アコムは平成21年にDCキャッシュワンを吸収合併しました。
旧DCキャッシュワンで借金が残っていて、アコムの過払い金よりも旧DCキャッシュワンの借金の方が多い場合、トータルでは借金が残ることになるため、信用情報がいわゆるブラックになってしまうので注意が必要です。
アコムの過払い金が旧DCキャッシュワンの借金よりも多ければ、ブラックになることはありません。
アプラス
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月程度
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割程度。
訴訟をすれば、おおむね返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から半年程度。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しようとすると、訴訟をしても和解にならない場合があります。
その場合、弁護士をつけて争ってきますので、過払い金を回収するまでの期間が半年以上になる場合もあります。
アペンタクル(ワイド)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
基本的に和解は困難なので裁判をする必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして判決を取っても、控訴してくることがあります。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
※現在では判決をとっても返金に応じず、強制執行をしても回収できるという保証はありません。
注意点
判決が出ても支払いに応じないので費用倒れになる可能性があります。
イオンクレジットサービス
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5~7割程度。
訴訟をすれば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から4ヵ月~半年程度
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
以前は訴訟をしないでも過払い利息を含めた全額で和解できていましたが、近年は和解ができなくなりました。
提訴すれば1回目の期日前に和解になることがほとんどです。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
基本的に和解は困難なので、裁判をする必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして判決を取っても、必ず控訴してきます。
控訴審判決が出て、しばらくすると返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額が返金されることがありますが、返金時期は未定です。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
注意点
平成23年8月に東京地方裁判所で破産手続開始決定を受けたため、過払い金の回収は見込めなくなりました。
エイワ
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から2~3ヵ月程度
和解可能な金額
基本的に和解は困難なので、裁判をする必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして判決を取っても、控訴してくる場合があります。
控訴審判決が出るまでは半年~10ヵ月程度かかります。
最近では、判決を取っても返金に応じなくなってきているので、今後は強制執行することも視野に入れる必要がありますので、返金時期は未定です。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
注意点
エイワも経営状況の悪化から、和解条件が過払い元金の半額程度で返還時期も半年~1年程度なので、最近では和解できないことが多いです。
このため、最近では判決を取ることが多いですが、判決が出ても返還に応じないので、今後は大幅に減額してでも、早期の返金に応じてくれれば和解した方がいいのか、時間をかけて強制執行までするのか判断が難しいところです。
エポスカード
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5~7割程度。
訴訟をすれば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から4ヵ月前後
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
以前は訴訟をしないでも過払い利息を含めた全額で和解できていましたが、昨年あたりから和解ができなくなりました。
訴訟をすれば1回目の期日前に和解になることがほとんどです。
同じ丸井グループで「ゼロファースト」という別会社がありましたが、現在はエポスカードに吸収されたので、エポスカードに過払い請求をすると旧ゼロファーストの取引も一緒に開示されます。
NISグループ(ニッシン)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
基本的に和解は困難なので、裁判をする必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして判決を取っても、必ず控訴してきますので、手続開始から返金までに半年~1年近くかかることもあります。
控訴審判決が出て、しばらくすると返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額が返金されることが多いです。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
注意点
平成22年にネオライングループに入ってから対応が急激に悪化し、その後、平成24年に破産したため、現在では回収不可能です。
オリエントコーポレーション
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割前後。
訴訟をすれば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は、地方裁判所での本人訴訟となります。
本人訴訟の場合、必然的に過払い金額が大きくなりますので、過払い利息を含めた全額を回収しようとすると、弁護士を選任して争ってくる場合があります。
ただし、本人訴訟の場合でも、過払い利息を含めたほぼ満額で和解が成立し、依頼者本人が裁判所に出廷する前に和解になることが多いです。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から半年~10ヵ月程度。
※ 最近では、過払い金額が大きいと、入金が半年程度先でないと和解できないケースも出てきています。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
平成6~7年以前のデータを完全に保有していないとの理由から、平成6~7年以前の履歴については、返済額だけがわかる履歴を開示してくることがありますが、その場合は、それを元に借入額を推定計算した上で提訴する必要があります。
最近では取引の途中で完済し、その後の再借入れまで期間が空いているような場合は取引の分断を主張してきます。
しかし、オリコのようなカード会社のキャッシングは、当初のカード作成時に基本契約を締結するだけで、その後は新たな基本契約を締結することはありませんので、取引の途中で長期の空白期間があっても一連計算することができます(最高裁平成19年6月7日判決)。
クレディセゾン
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5~7割程度。
訴訟をすれば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は、地方裁判所での本人訴訟となります。
ただし、本人訴訟の場合でも、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額で和解が成立することが多いので、依頼者本人が裁判所に出廷しないで済む場合がほとんどです。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から3~4ヵ月程度
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
以前は訴訟をしないでも過払い利息を含めた全額で和解できていましたが、近年は和解ができなくなりました。
しかし、訴訟をすれば1回目の期日前に和解になることがほとんどです。
同じセゾングループで「セゾンファンデックス」という別会社がありますが、こちらも訴訟をすれば、おおむね最終取引日までの過払い利息を含めた過払い金全額に近い金額で和解できますが、クレディセゾンのように返還日までの過払い利息までとなると判決を取る必要があります。
JCB(ジェーシービー)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の7~8割程度。
訴訟をすれば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は、地方裁判所での本人訴訟となります。
本人訴訟の場合でも、最終取引日までの過払い利息を含めた過払い金程度であれば和解が成立することが多いので、依頼者本人が裁判所に出廷しないで済む場合がほとんどです。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から3~4ヵ月程度
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
以前は訴訟をしないでも過払い利息を含めた過払い金全額で和解できていましたが、近年は和解が難しくなってきています。
訴訟をすれば1回目の期日前に和解になることがほとんどですが、事案によっては弁護士をつけて争ってくることもあります。
ワイジェイカード
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
過払い元金の7割前後。
それ以上回収したい場合は、裁判をする必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして第一審で判決を取っても、取引の分断等の争点があると控訴してくることがあります。
その場合、手続開始から返金までに半年~1年程度かかります。
控訴審判決が出れば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額が返金されます。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
注意点
全額回収したい場合は、裁判をしても和解せずに判決を取る必要があります。
判決を取れば、控訴してくることもありますが、最終的には強制執行されることを避けるために、全額の返還に応じます。
新生フィナンシャル(レイク)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割前後。 訴訟をすれば返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は、地方裁判所での本人訴訟となります。
本人訴訟の場合、必然的に過払い金額が大きくなりますので、過払い利息を含めた全額を回収しようとすると、弁護士を選任して争ってくる場合があります。
ただし、本人訴訟の場合でも、過払い利息を含めたほぼ満額で和解が成立し、依頼者本人が裁判所に出廷する前に和解になることが多いです。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から半年程度
※ 提訴しても1~2回目の期日前に和解になり、和解後3ヵ月程度で入金になることが多いです。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収します。
注意点
サラ金業者の中では、比較的過払い請求の対応がよいといえます(ただし、訴訟をした場合)。
しかし、平成5年10月以前の履歴を開示しないため、それよりも前から取引がある場合は冒頭残高を無視して計算(いわゆる「0スタート計算」)するか、古い契約書等が残っていれば、それを元に推定計算した上で提訴する必要があります。
グループ会社に新生カード(旧GEカード、旧GCカード)という別会社がありましたが、現在はアプラスと合併しました。
新生パーソナルローン(シンキ)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割前後。
訴訟をすれば、おおむね最終取引日までの過払い利息を含めた金額であれば和解できることが多いですが、過払い金額が大きいと和解できない場合もあります。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から半年前後
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を目指しますので、最近では和解が成立せずに判決になることもあります。
判決後は控訴しないですぐに返金に応じます。
注意点
新生パーソナルローン(シンキ)は新生フィナンシャル(レイク)と同じ新生銀行グループですが、新生フィナンシャルより明らかに対応が悪いです。
とはいえ、新生銀行グループにいる限りは破綻する可能性はないでしょうから、より多くの過払い金を回収したいのであれば、多少時間はかかっても訴訟をした方がよいと思います。
CFJ(アイク、ディック、ユニマット)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割前後。
訴訟をすれば、おおむね最終取引日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能ですが、案件によっては和解できずに判決になる場合があります。
過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は、地方裁判所での本人訴訟となります。
本人訴訟の場合、過払い元金全額~元金の9割程度であれば和解できることが多いですが、過払い利息まで含めた金額の回収を目指すのであれば、判決を取ることも視野に入れる必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から4ヵ月~半年前後
※ 財務状況の悪化で、今後は遅れる可能性があります。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収を目指しますが、最近は過払い利息まで回収しようとすると早期に和解できない場合も多いです。
よって、依頼者の意向や費用対効果を考え、過払い元金+αで和解することもあります。
注意点
CFJも財務状況の悪化で、今後は予断を許さない状況です。
そのため、時間をかけてでも過払い利息を含めた全額の回収を目指すのか、早期に過払い元金+α程度で和解した方がよいのか判断が悩ましいところです。
セゾンファンデックス
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5~7割程度。
訴訟をすれば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から3~4ヵ月程度
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
以前は訴訟をしないでも過払い利息を含めた全額で和解できていましたが、近年は和解ができなくなりました。
訴訟をすれば1~2回目の期日前に和解になることもありますが、返金日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収する場合は、判決になることもあります。
そのため、同じセゾングループの「クレディセゾン」の方が過払いの対応は良好といえます。
セディナ
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~3ヵ月程度
※ セディナは平成21年に旧OMCカード、旧セントラルファイナンス、旧クオークが合併してできた会社ですが、取引履歴も合併前の各会社の部署から開示され、履歴の書式や開示期間もそれぞれ異なります。
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5~7割程度。
訴訟をすれば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は、地方裁判所での本人訴訟となります。
本人訴訟の場合でも、最終取引日までの過払い利息を含めた過払い金全額で和解が成立することが多いので、依頼者本人が裁判所に出廷しないで済む場合がほとんどです。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から4~8ヵ月程度
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
過払い請求の対応も合併前の3社ごとに若干異なりますが、いずれの場合も提訴すれば返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
3社それぞれで取引がある場合、トータルで過払いになっていない段階で、司法書士等の専門家に依頼をすると信用情報がいわゆるブラックになりますので注意が必要です。
ゼロファースト
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしなくても、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から3ヵ月前後
当事務所の回収基準
返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
現在はエポスカードに吸収されたので、ゼロファーストで借り入れがあった場合は、エポスカードに対して請求することになります。
三菱UFJニコス
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2か月程度
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の7割~全額程度。
訴訟をすれば、おおむね返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は、地方裁判所での本人訴訟となります。
ただし、本人訴訟の場合でも、過払い元金にある程度の過払い利息を含めた金額であれば、和解が成立することが多いので、依頼者本人が裁判所に出廷しないで済む場合もあります。
本人訴訟の場合、必然的に過払い金額が大きくなりますので、過払い利息を含めた全額を回収しようとすると、弁護士を選任して争ってきます。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から半年程度
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
平成7年以前の履歴を開示しないため、それよりも前から取引がある場合は、冒頭残高を無視して計算(いわゆる「0スタート計算」)するか、通帳の引落記録等が残っていれば、それを元に推定計算した上で提訴する必要があります。
旧日本信販系の取引で過払いでも、ニコスは旧UFJカード、旧DCカードを吸収合併しているので、トータルで過払いになっていない段階で、司法書士等の専門家に依頼をすると信用情報がいわゆるブラックになりますので注意が必要です。
最近は同じ契約の取引でも1年以上の空白期間がある場合は取引の分断を主張してくることがあります。
ニッセンジーイークレジット
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5~7割程度。
訴訟をすれば、過払い金元金のみであれば、早期に和解が可能です。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から4ヵ月~半年程度
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収しています。
注意点
以前は訴訟をしないでも過払い利息を含めた全額で和解できていましたが、近年は和解ができなくなりました。
最近では、訴訟をしても過払い利息の返還には素直に応じませんが、おおむね最終取引日までの過払い利息を含めた過払い金全額に近い金額であれば和解できることが多いです。
しかし、完済してからかなりの年数が経っているような場合に、返還日までの過払い利息まで回収するとなると、今後は判決を取ることも視野に入れて過払い請求をする必要がありそうです。
ネオラインキャピタル
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
基本的に和解は困難なので、裁判をする必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして判決を取っても必ず控訴してきますので、手続開始から返金までに半年~1年近くかかることもあります。
控訴審判決が出て、しばらくすると返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額が返金されます。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
注意点
現在では破産したため回収することはできません。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割程度。訴訟をすれば返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額の回収が可能です。
過払い元金が司法書士の訴訟代理権の上限である140万円を超えた場合は地方裁判所での本人訴訟となります。
本人訴訟の場合、必然的に過払い金額が大きくなりますので、過払い利息を含めた全額を回収しようとすると、弁護士を選任して争ってくる場合があります。
ただし、本人訴訟の場合でも、過払い元金全額に多少の過払い利息を含めた程度の金額であれば、依頼者本人が裁判所に出廷する前に和解になることがほとんどです。
過払い金が返還されるまでの期間
手続開始から半年前後
※ 当事務所では全件訴訟のため、訴訟しないで和解した場合の期間はわかりませんが、訴訟した方が早く回収できるのは確実と思われます。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をした上で、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額を回収します。
過払い元金が140万円を超える本人訴訟の場合、過払い元金+αで和解し、依頼者本人が出廷しないで済むケースが多いです。
注意点
プロミスは平成22年に三洋信販、平成23年にアットローンをそれぞれ吸収合併しました。
旧三洋信販もしくは旧アットローンで借金が残っていて、プロミスの過払い金よりも旧三洋信販もしくは旧アットローンの借金の方が多い場合、トータルでは借金が残ることになるため、信用情報がいわゆるブラックになってしまうので注意が必要です。
プロミスの過払い金が旧三洋信販もしくは旧アットローンの借金よりも多ければ、ブラックになることはありません。
ライフカード
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割程度。
訴訟をしても5~7割以上での和解は困難なので、それ以上回収したい場合は判決を取る必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして判決を取り、控訴されなかった場合は4ヵ月~半年前後。
控訴された場合は半年から10ヵ月前後。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
ただし、第一審で判決を取っても、ライフカードが控訴してくることがあります。
判決を取った場合、返還日までの過払い利息を付加した過払い金全額が返金されます。
注意点
平成23年7月に、ライフカードのキャッシング部門がアイフルに吸収合併されたため、旧ライフで過払い金が発生していても、請求先はアイフルになります。
過払い金が発生しないショッピング部門は「ライフカード株式会社」が引き継ぎました。
日本保証(武富士)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1ヵ月前後
和解可能な金額
過払い元金の1~2割。
それ以上を回収したい場合は、裁判をする必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして第一審で判決を取っても、控訴してくることがあり、 その場合は手続開始から返金までに半年~1年程度かかります。
控訴審判決が出れば、返還日までの過払い利息を含めた過払い金全額が返金されます。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。
注意点
和解の場合、裁判をしないと1割程度、裁判をしても良くて5割程度です。
よって、全額回収したい場合は、裁判をしても和解せずに判決を取る必要があります。
判決を取れば、控訴してくることもありますが、最終的には強制執行されることを避けるために全額の返還に応じます。
旧ロプロは平成21年に会社更生の申し立てをしたため、旧日栄で発生した過払い金については回収できませんが、会社更生後に合併した旧ステーションファイナンス、旧プリーバで発生した過払い金は回収できます。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
最新の投稿
- 2026年2月5日ITO総合法律事務所から赤い封筒が届いたときの対処法や時効援用について
- 2025年8月6日三菱HCキャピタル債権回収株式会社の時効援用
- 2025年8月5日エイワの取り立てと裁判や支払督促の時効援用
- 2025年8月4日沖縄債権回収サービス(おきなわサービサー)の時効援用