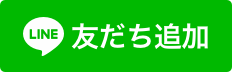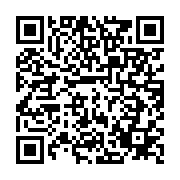公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2025年9月25日
時効の中断(更新)するのはどんな時?債務承認のリスクなど
時効の「更新」と「完成猶予」
貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、最後に返済したときから5年が経過すれば、絶対に時効が成立するというわけではありません。
なぜなら、時効には中断(更新)事由というものがあるからです。
債権者である貸主保護の観点からも時効を中断(更新)させるような事由があった場合にまで、借主に消滅時効の援用を認めるのは公平ではないと考えられています。
よって、中断(更新)事由に該当するような行為があった場合は、消滅時効が成立することはありません。
旧民法では時効の「中断」と「停止」の2つがありましたが、2020年の民法改正で「更新」と「完成猶予」に変わりました。
時効の更新と完成猶予とは
- 「時効の更新」・・・時効期間をリセットしてゼロからカウントし直すこと
- 「時効の完成猶予」・・・時効の進行を一時的にストップさせること
時効が更新とは、時効期間が一時的に中断するのではなく、すべてリセットされるということです。
旧民法では「中断」といわれていたため、時効が一時停止するだけと誤解されていることが多かったので、新民法で「更新」に変わりました。
例えば、最後の返済から4年11ヶ月が経過し、時効の完成まであと1ヶ月だったとしても、時効が更新した場合は時効期間がリセットされてゼロからスタートします。
時効の完成猶予とは、時効の成立を一時的にストップさせることで、以下のような事由が該当します。
時効の完成猶予に該当する行為
- 内容証明郵便などで催告した
- 裁判を起こした(訴訟、支払督促、調停など)
- 強制執行の申し立てをした
内容証明郵便で催告をおこなうと、時効の完成を6か月間だけ猶予させることができます。
裁判を起こすと判決や和解によって手続きが終了するまでの間は時効の完成が猶予され、判決などの債務名義が確定した段階で時効が更新します。
強制執行も同様で、仮処分や仮差押をおこなった場合も時効の完成が猶予されます。
ここがポイント!
時効の更新事由があると時効はゼロから再スタートする
時効の更新事由に該当するのはどんな時?
時効の更新事由に該当する行為はいくつかあるのですが「裁判手続きが確定した場合」と「債務者が債務を承認した場合」の2つに分けられます。
単に債権者から請求書が送られてきているだけでは、時効が更新することはなく、裁判を起こされて判決などを取られなければ時効は更新しません。
債務の承認とは、債務者が返済をしたり、債務を認める書面にサインしたり、実際に支払いをしていなくても「少し待って欲しい」「少しでも減額してくれないか」「分割払いにしてもらえないか」等と発言をした場合が該当します
一部返済や書面の取り交わしがなされた場合は証拠が残りますが、口頭での発言のみだと債務承認に該当するかどうか判断が難しい場合があり、消滅時効が成立しているかどうかが裁判で争われることもあります。
当初の貸主から債権回収会社(サービサー)などに債権譲渡があっても時効は更新しません。
ここがポイント!
単なる請求書では時効は更新しない
裁判上の請求とは
債権者である貸主からの請求であれば、どのような請求であっても時効を更新するわけではなく、消滅時効を更新させるためには裁判上の請求である必要があります。
裁判上の請求にもいくつかあり、借金の消滅時効で代表的な裁判上の請求は「訴訟」と「支払督促」の2つです。
よって、単に貸主である債権者から電話や催告書で請求を受けているだけであれば時効は更新せず、最後の返済から5年の経過で時効が成立します。
消滅時効を更新させる裁判上の請求のうち、訴訟というのは通常の民事訴訟のことで、原告である債権者が訴状を裁判所に提出したときに時効の完成が猶予され、確定判決などによって権利が確定したときに時効が更新します。
裁判所から訴状が届いたにもかかわらず放置してしまうと欠席判決といって債権者の言い分どおりの判決が出てしまいます。
支払督促は債務者である借主が異議を述べない限り、債権者が裁判所に出頭することなく、裁判所が借主に対して「金何万円を支払え」という命令を出してくれるもので判決と同じ効力があり、その利便性から多くの債権者が利用しています。
支払督促の場合も支払督促申立書が提出された時点で時効の完成が猶予され、最終的に仮執行宣言付き支払督促が確定した段階で時効が更新します。
これに対して、すでに判決を取られている場合、消滅時効の成立は判決が確定したときから10年に延長されます。
判決に限らず、裁判上の調停や和解が成立した場合も時効は10年に延長されます。
よって、判決等を取られている場合でも、判決の確定や和解もしくは調停の成立から10年が経過すれば消滅時効が完成するわけです。
実務上も、債権者が過去に判決を取ったものの、その後も債務者が1度も返済せずに10年以上経過した事案で、消滅時効を援用できることがあります。
また、原告が訴訟を取り下げたり、訴訟が却下された場合は時効は更新しません。
ここがポイント!
判決を取られると時効は10年に延長される
催告とは
時効を更新させるには裁判上の請求であることが大原則ですが、催告でも6ヶ月間は時効の完成を猶予させることができます。
ただし、催告をしただけでは時効が更新することはないので、その後に裁判上の請求をしなかった場合は6ヶ月後に消滅時効が完成してしまいます。
実務上は、時効の完成が数日後に迫っている場合に配達証明付の内容証明郵便で催告をおこない、その後6ヶ月の間に訴訟もしくは支払督促を提起することが多いです。
なお、催告による時効の完成猶予は1回しか使うことができません。
ここがポイント!
催告によって時効の完成を6か月間猶予させることができる
公示送達による時効の更新
訴訟では債権者である原告が訴状を裁判所に提出しますが、時効の更新(中断)は「訴状が裁判所に提出されたとき」に生じます。
つまり、訴訟では訴状が相手に送達される「前」に時効の更新(中断)の効力が発生することになります。
この点、催告は内容証明郵便などによる催告書が債務者に「到達」しなければ、時効の完成猶予の効力が発生しません。
よって、相手が行方不明のときには、催告によって時効の完成を猶予させることはできません。
これに対して、訴訟では相手が行方不明であっても訴状を裁判所に提出した時点で時効が更新(中断)します。
とはいえ、訴訟でも相手が行方不明だと訴状を被告である借主に送達することができません。
しかし、裁判では「公示送達」という手続きがあります。
公示送達では裁判所の掲示版に「原告から被告に対し訴訟が出されたので訴状を取りに来てください。2週間経過しても取りに来ない場合は送達されたものとみなす」といった内容を掲示します。
その後、実際に2週間が経過した場合は、訴状が被告である借主に送達されたものとみなして裁判が進行します。
裁判が進行するといっても、実際には被告である債務者は行方不明で裁判所に出廷することはないので、原告である債権者の主張どおりの判決が出ることになります。
多額の借金を背負った債務者が行方不明になることは決して珍しいことではありません。
そのような場合、債権者が行方不明の債務者に対して、公示送達による裁判で時効を更新(中断)させることがあるので、債務者が気づかないうちに裁判を起こされて時効が更新していることがあります。
ここがポイント!
債務者が行方不明でも公示送達による裁判で時効が更新することがある
債務承認とは
債務の承認は時効更新事由の中で一番重要といわれています。
代表的な承認は以下のとおりです。
債務承認に該当する行為
- 一部弁済
- 債務を認める書面の取り交わし
- 支払い猶予や減額(分割)払いのお願い
債務者が借金の一部を返済した場合、時効の更新は借金の全部に及びます。
例えば、100万円の借金がある場合にわずか1000円でも弁済してしまった場合は、原則的に時効は更新してしまいます。
よって、少額だからといって1回でも返済してしまうと、あとから消滅時効の援用はできないのが大原則です。
債務を認める示談書や和解書、合意書を取り交わした場合も債務承認に該当して時効が更新します。
支払猶予は債務者が債権者に支払延期願いなどの書面を送付したり、貸主に対して「もう少し待ってください」などと支払猶予のお願いをすることです。
これ以外にも借金を支払う前提で減額交渉した場合なども承認に該当します。
いずれの場合においても、すでに時効が成立しているにもかかわらず、債務者がそれを知らずに一部弁済や支払猶予願いをしてしまっても、消滅時効の主張ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
債権者は時効期間経過後であっても、債務者の無知に乗じて、催告書などで請求をしてくることがあります。
もし、債務者が消滅時効を援用せずに少額であっても一部返済をした場合、債務者の時効援用権が喪失するのが原則です。
ただし、事案によっては債権者からの時効援用権喪失の主張が認められない場合もあるので、時効期間経過後に一部弁済したからといって、一律に債務者の時効援用権が喪失するというわけではなく、最終的には裁判で決着をつけることになります。
ここがポイント!
時効期間経過後に一部弁済すると時効援用権を喪失するのが原則だが例外もある
消滅時効完済後の債務承認に関する最高裁判決
消滅時効完成後の債務承認と時効援用については、以下の最高裁判決があります。
債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。
けだし、時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当であるからである。
また、かく解しても、永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものでもない。
引用元:昭和41年4月20日最高裁判決
昭和41年の最高裁判決は、借主側からの消滅時効の援用は信義則照らして許されないとしています。
貸金業者の中にはこの判決を逆手にとって、時効期間が経過しているにもかかわらず、借主に請求をして借主が消滅時効の援用をしないと見るや、1000円程度の少額金を返済させたうえで、貸金訴訟を起こして貸金の回収を図ろうという動きがあります。
近年はすでに廃業した貸金業者から債権を買い取った業者が、すでに最終取引日から10年以上経過しているような場合でも、借主に対して請求を再開する例が多く報告されています。
こうした業者は「1000円でもいいから払ってくれ」等と言って、なんとか借主に債務承認させようとしてきます。
こういった場合に、貸金訴訟において借主が消滅時効の主張をしても、貸金業者側は上記の最高裁判決を利用し、消滅時効の主張は信義則に反し許されないと主張してきます。
しかし、この最高裁判決は単に債務承認があれば時効を援用する権利が消滅するとしているわけではなく、時効期間経過後に債務承認があったときは時効の援用を認めないことが信義則に照らして相当であると判断しただけです。
つまり、個別の事情の照らして時効の援用が信義則に反しないと思えるような場合は、消滅時効の主張が可能となる場合があるということです。
例えば、取引経験や法的知識に勝る貸金業者が消滅時効の完成を知りながら、借主の無知に乗じて強引に一部金を返済させ、その後は残元金のみならず多額の遅延損害金を含めて請求してきたような場合は、時効制度の趣旨や公平の観点からも時効の援用を認めるべきと考えられます。
これまでの裁判例でも、時効期間経過後に債務承認をしても貸主の請求に問題があるとして、消滅時効の援用が認められているケースは多々あります。
最終的には個別の事情を考慮したうえで裁判官の判断によることになるので、単に時効の成立を知らなかったというだけでは、上記の最高裁判決によって時効の援用は認められません。
これに対して、貸金業者から違法な取り立てや強引な請求によって弁済をしてしまったり、「〇円払えばあとは何とかする」等と甘い言葉をかけられて支払ってしまった場合には、消滅時効の援用が可能となる場合もあります。
ここがポイント!
個別の事情によっては時効期間経過後に債務承認があっても時効が認められる場合がある
時効にならない場合
貸金業者の借金は5年で時効になってしまうので、通常は債権者も時効が成立する前に裁判や支払督促を提起してきます。
裁判上の請求には、訴訟や支払督促以外の給料の差押えなども含まれます。
更新事由がある場合、債務者は消滅時効の援用をすることができません。
時効成立まであとわずかであれば、時効が成立することを期待して、そのまま様子を見るというのも一つの選択です。
しかし、時効成立まで何年も残っており、返済するだけの収入があるのであれば、そのまま放っておくのではなく、債権者と分割で支払う和解(いわゆる任意整理)をした方が良い場合もあります。
あわせて読みたい
司法書士は内容証明郵便による消滅時効の援用はもちろんのこと、借金の返済に関する和解交渉を代理人としておこなうこともできます。
よって、当初は消滅時効の主張をするつもりでも、あとで更新事由があることが分かり、時効の援用ができないような場合、司法書士にお願いしておけば、そのまま借金の返済に関する和解交渉に移行することも可能です。
また、返済の見込みが立たない場合は自己破産に移行することもできるので、たとえ更新事由がある場合でも安心です。
ここがポイント!
更新事由がある場合は、そのまま任意整理や自己破産に移行できる
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。
債権回収会社などから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
最新の投稿
- 2025年8月6日三菱HCキャピタル債権回収株式会社の時効援用
- 2025年8月5日エイワの取り立てと裁判や支払督促の時効援用
- 2025年8月4日沖縄債権回収サービス(おきなわサービサー)の時効援用
- 2025年1月14日0120309845のプライメックスキャピタル(キャスコ)の時効援用